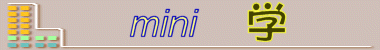 |
2007.3.31 |
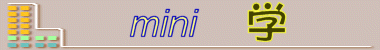 |
2007.3.31 |
肩こりや手足のしびれ頭痛などが、実は枕に原因があることが考えられるそうです。 そこで枕について調べてみました。 人はなぜ枕を必要とするのでしょうか? 江戸時代以前には、髷(まげ)の形を崩さないように、首を木製の小さな台(箱枕)に乗せて寝るのが一般的でした。 またその材質として、木枕の他に石枕や陶枕・籐枕・竹枕などがありました。 人間意外の動物で、睡眠するために枕を必要とするものはいません、 ではなぜ人間が枕を必要とするかというと、二足歩行をするようになったからだと考えられます。 二足歩行をする人間は、身体の体積に対して大容量な脳とそれを保護する頭蓋骨の重さを、背骨で支えなくてはなりません。 その背骨は、ゆるいS字を描くようになり、ショックアブソーバーの機能を果たしているのです。 このS字を描く背骨の延長に頭部があるわけで、枕なしで仰向けになるとS字に無理がかかり、肩痛・腰痛などの原因にもなります。 頭の下に枕を置くことで、自然なS字が保たれてゆっくり休むことができるということです。 「寿命三寸楽四寸」という言葉があり、髷の形を崩さずに楽に寝るには四寸の高さが必要だが、長寿のためには低い三寸の高さが良い。 という意味だそうですが、現代人には三寸(約9cm)は高すぎで、3〜6cmが良いとされています。 枕は高さだけでなく、素材にも左右されます、睡眠中に発散される水分や熱を吸収してくれる素材。 昔からの自然の素材としては、小豆や蕎麦殻などが代表的といえますが、現代では化学製品や羽毛などがあります。 枕が替わると眠れない、という人がいるようですが、自分に合った枕選びは意外と重要なのかもしれません。 枕といえば、「枕投げ」を思い出す人も多いでしょう。 修学旅行=枕投げ、という一種の行事のようになっているようですが、その起源は分かりません。 少なくてもこのようなことが始まったのは、それほど古いことではないと考えられます。 箱枕などはもし投げ合ったら大ケガをしますから、投げ合うことには適していませんでした。 枕に関してのいくつかの言葉。 「枕を高くする」 何の不安もなしに安心して寝る。 「枕を並べる」 「枕を共にする」 (男女が)ともに寝る。 「枕を交わす」 男女が一緒に寝る。情交する。 「枕を重ねる」 男女が何度も同衾する。 「枕を濡らす」 悲しみに堪えず、夜ひそかに涙を流す。 枕詞(まくらことば)といえば、主として和歌に用いられる修辞で、特定の語の前に置かれます。 歌の意味には直接的に関係しない言葉ですが、語調を整えたりある種の情緒を添える役目をします。 「茜さす(あかねさす)」は、日・昼・紫・照る・君 の前に、 「紅の(くれなゐの)」は、色・うつし心・浅 に、 「垂乳根の(たらちねの)」は、母 の前に付けられます。 また、「枕言葉」となると、司会や挨拶の前に挿入される飾り言葉とでもいうのでしょうか、 例えば、春の季節なら、「花は咲き鳥はさえずる春爛漫の・・・」 というように始まり、挨拶の言葉を引き立てる一種の定型的なものです。 落語の場合は本筋の噺の前に、小ばなしやその時期にあった世間話などを入れることを枕といいます。 これによって、客を引き付けたり、客の反応を見てその後の本題の噺を替えたりするそうです。 鉄道のレールの下に置くのを「枕木」といいます。 かつては木製の枕木が主流だったのですが、寿命が短い、狂いが生じやすいなどの欠点がありました。 近年では、コンクリートやプラスチック発泡体などの合成材を使用した枕木が増えてきています。 木製ではないため、「まくらぎ」というように表現しているそうです。 レールもやはり休みたいのでしょうか・・・ ブルートレインでの旅行、 憧れです。 規則的なレールの継ぎ目の音を聴きながら、憧れの人とのピロートーク。
|