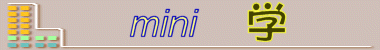 |
2006.9.9 |
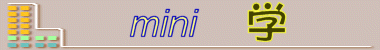 |
2006.9.9 |
たとえば今、このサイトを見ている人はパソコンを立ち上げているはずです。 そのパソコンを組み立てるには、数多くのネジが使われています。 ふだん何気なく生活している中で、身の回りにはあふれるほどのネジ類が使われています。 朝目覚まし時計で起こされる、 その目覚まし時計の中はネジだらけ。 最近はマイコンチップを使用した時計がほとんどですが、それでも沢山のネジは使われています。 日本語では「螺子」と書きます、英語では screw . このネジはいったい誰が発明したのか、またその起源など実は定かではありません。 しかし、最初に利用したのは太古の人々であったろうといわれています。 細長い巻貝の螺旋(らせん)を利用して、ものに穴を開けたのがネジの最初だろうとされているからです。 もっとはっきりとした形でネジを使い始めたのは、古代ギリシャの哲人アルキメデスだといわれています。 木製の心棒に螺旋状の板を打ち付けて筒に入れ、これを回転させることでネジのピッチ間に水を閉じ込めて上へと押し上げていくものです。 主に灌漑用水の汲み上げや、船底にたまった水の排水に使われました。 またその少し後に、数学者ヘロンは、木の棒にネジ山を刻んで、オリーブや葡萄などの果汁を絞るための圧縮機を作りました。 この方式は後々色々な方面で改良されて、今のプレス機の原型となっています。 また、天才レオナルド・ダビンチは、こうしたプレス機などに利用するネジを作るための機械である「ネジ切り旋盤」を作ったといわれています。 実は、このネジの原理と古代エジプトのピラミッド造りには密接な関係があります。 ピラミッドの工法は、長い坂道を造り、これを利用して重い石を高いところまで運んだとされています。 「斜面の原理」と呼ばれる力の分散を利用したもので、この原理を応用したものがネジなのです。 直角三角形の紙を丸い棒に巻きつけると、そこに螺旋の筋道が出来る、この筋道に沿ってネジ山を切れば、 出来上がったネジ本体を回すことで、斜面の原理になります。 さて、身近な部品としてのネジですが、日本に入ってきたのは、種子島に火縄銃が渡ってきたときだとされています。 銃底をふさぐ「尾栓ネジ」と呼ばれるものですが、国内で銃を作るのにあたって、当時の刀鍛冶がネジを作るのは容易でなかったようです。 一口にネジといってもその種類は豊富で、木材への締め付け用である「木ネジ」、鉄板への締め付けでは「タッピングネジ」。 また、オネジとメネジの組み合わせで使うボルト・ナット。 そのオネジとメネジにもネジの目の違いがあり、合わないものを無理やりにネジ込むと破損します。 一般的には、日本の規格であるJISや国際規格のISOネジがあります。 ネジの頭の部分の溝にも種類があり、マイナスやプラスがありますが、 ネジを締め付けるために最も良い溝というのがあるそうです。 それは、ネジの頭部に四角い穴とその底に正四角錘の凹みがあるものだそうです。 ネジとネジ回しがぴったりとフィットし、最も締め付けが容易で効率があるといわれています。 20世紀初頭に考案されたにもかかわらず、産業界ではマイナスやプラスネジが多用されています。 その理由として、自動化の産業界では、「締めすぎ」という現象はあまり好まれないということのようです。 ネジは、締めて終わりではなく、外すこともあるということでしょうか。 ネジの役目として、 物と物を締め付けて固定させる、また、物と物を接合・結合させる。 ネジの回転を直線移動に換えて物の長さを測定する。(マイクロメーター等) また回転運動により物を移動させる。 その回転移動により物を圧搾・圧縮する。 締めることで密着させる、 日常よく利用するものとしては、ペットボトルの栓等の密閉用。 ネジは、きっちり締まっていてこそ、その役目を果たします。 しかし、今回調べてみて新しいことが分かりました。 締めすぎ(締まりすぎ)は、良くない! 少し安心したような・・・
|