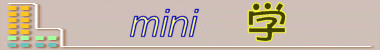 |
2006.12.9 |
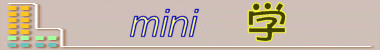 |
2006.12.9 |
身のまわりに電子機器が増え、便利な世の中になっています。 特にパソコンや携帯電話などは、次々に新機種が開発され、ついていけないほど。 これらの普及の影には、もちろんIT産業が深く関係しています。 ITのTであるテクノロジー(技術)の面で言えば、高性能・小型化・大容量・・・ などがありますが、記憶媒体(メモリー)の容量は日進月歩で増大化をたどっています。 私が最初に購入したパソコンは、いわゆる98シリーズといわれるもので、1枚のフロッピーディスクから立ち上げるものでした。 ワープロやその他のソフトは、それぞれ使うごとにフロッピーから立ち上げなおす必要があり、windows の登場は画期的なものでした。 フロッピーディスクの容量は、2HDタイプで1.44Mb(1.25Mb) でしたから、最初に購入した 135Mb のハードディスクはフロッピー100枚相当の容量であり、じゅうぶん満足できるものでした。 このハードディスクの容量は、あれよあれよと増大し、数百Mb(メガバイト) から Gb(ギガバイト)の時代になり、今では Tb (テラバイト)にまで。 この数字の容量は、10の3乗で増えていくのですから凄いものです。 たとえば数字の10があって、その3乗つまり1000は K(キロ)6乗が M (メガ)9乗が G (ギガ)・・・ となります。 小さい方(マイナス)では、-3乗がミリで次にマイクロ・ナノ・ピコ・・・ となっていきます。 通常私たちが使う数字の単位としては、その辺の範囲だと思います。 ちなみにこの数字の単位を日本語で表すと、10の12乗であるテラは、「兆」になります。 金額でいえば、億の単位でも縁が無いのに、兆という数字は国家予算的数字、この縁のない兆という単位に、せめてハードディスクの世界で満足感を味わいましょう。 参考までにこの単位を日本語で表すと、 一 十 百 千 万 億 兆 京 垓 予 穣 溝 潤 正 載 極 恒河沙 阿僧祇 那由多 不可思議 無量大数 ということになり、最後の無量大数は10の68乗です。 この中で、10の52乗の恒河沙(ごうがしゃ)は、 「ガンジス川の無数の砂」という意味だそうで、それだけでも気が遠くなりそうなのに、その上があるというのですから、まさに不可思議であり、それ以上はもう数え切れない無量の大きな数字という半ば投げやり的です。 数字の単位について整理してみましたが、次は基準です、たとえば1mの長さの基準はどのようにして作られたのでしょうか。 昔の人たちは、身のまわりのもので長さや重さの基準を作っていました。 たとえば親指の幅を1インチ(約2.54cm)、足のつま先からかかとまでを1フィートとしたりしていましたが、これは個人差があります。 国際単位であるメートル法では、地球一周(縦周り)の4千万分の1の長さ(北極から赤道までの長さの1千万分の1の長さ)を1mとしています。 重さの基準では、一辺が10cmの立方体の容器に入る水の重さを1Kgとしています。 昭和34年のメートル法施行により、商店で量り(はかり)売りするものは、g(kg)表示の量りになりました。 それまでは尺貫法の量りで、貫や匁(もんめ)という単位でした。 この匁という単位は、中国から伝わった「開元通宝」である一文銭一枚の重さを基準にしているそうです。 本来「文目」と書くべきなのですが文メと書いているうちに合体して匁になったとか。 この一文銭の四角い穴に紐を通して1000枚まとめたものが1貫で、メートル法での3.75Kgになります。 私が子供の頃は、「味噌を100匁買ってきて、」などとお使いを頼まれた記憶があり、後に400gくらいで一つの単位になっていたようですが、やはり100匁くらいが買いやすい(売りやすい)量なのでしょうか。 一円玉が1グラムであるということは良く知られていますが、五円玉の重さをご存知でしょうか。 五円玉の重さは3.75gで、つまり昔の一文銭と同じだそうです、機会があったら量ってみてください。 ちょっと気になる数字。 1)酒のビンのことを今でも一升瓶といいますが、要するに1.8リットル。 2)船舶の走る速さをノットで表しますが、これは1海里を1時間で移動する速さだそうで、1ノットは時速約1.8kmだそうです。 3)古代ギリシャには、スダディオンという単位があり、この基準は、太陽が地平線に顔を出し始めてから全部の姿を表すまでの間に歩いた距離で、約180m。 4)直線の角度=180度。 5)今年は平成18年ということで、お後がよろしいようで。
|