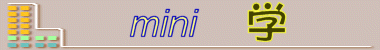 |
2008.8.16 |
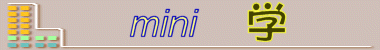 |
2008.8.16 |
相手を誘うときの言葉として、 「お茶を飲みに行きませんか」 というのは、今でも通用するでしょうか。 お茶を飲んで一息つくことをティーブレイクといいますが、 「お茶しませんか・・・」 というのは、日本独特の言葉の発明かもしれません。 「お茶の時間」に飲むのは、日本茶に限らずコーヒーであったり紅茶であったり、ハーブティー等々ですが、 それらに共通するのは、刺激を与えてくれるカフェインあるいは安らぎを与えてくれるアロマでもあります。 くつろぎの場、それがお茶の時間です。 お茶を最初に発見したのは、紀元前2800年ごろ、中国を治めていた炎帝神農といわれています。 神農が夕食の支度をするため釜で湯を沸かしていると、風で飛ばされてきた椿の葉が釜の中に落ちました。 その葉が、実はお茶の葉だったというのです。 (茶はツバキ科の植物です) 神農は、「神農本草経」という薬学書の中でその効能について、 「のどの渇きを癒し、睡眠欲を抑え、心臓を喜ばせ、元気付ける。」 と記しています。 漢の時代(紀元前1世紀)、お茶は単独ではなく、みかんの皮、ねぎ、しょうがなどと混ぜて、お吸い物として飲まれていたという記録もあるようです。 明の時代になると、貴族と富裕市民に限られていた喫茶の習慣が、一般市民へと普及していきました。 奈良・平安時代に、最澄、空海、永忠などの留学僧が、唐よりお茶の種子を持ち帰ったのが、わが国のお茶の始まりとされていますが、それは薬として用いられたようです。 平安初期(815年)の『日本後記』には、 「嵯峨天皇に大僧都永忠が近江の梵釈寺において茶を煎じて奉った」と記述されています。 これが、わが国における日本茶の喫茶に関する最初の記述といわれています。 南北朝時代の『異制庭訓往来』には、当時の名茶産地が記されています。 京都各地および大和、伊賀、伊勢、駿河、武蔵では、寺院、寺領の茶園を中心に茶栽培が行われるようになりました。 さらに、お茶栽培の北限といわれる茨城の奥久慈のお茶も14世紀に始まったといわれています。 現代の日本人の生活は大きく変わり、一般の家庭でも日本茶だけでなく、烏龍茶などが注目されています。 1979年には、伊藤園が中国の烏龍茶を日本人向けにアレンジして製品化し、烏龍茶の大ブームを起こしました。 今では、缶入りやペットボトル、紙パック製品が陳列棚にずらりと並んでいます。 さらにお茶の有効成分の活用によるカテキン染色技術や、サプリメント製品など、飲料に限定しないお茶の利用が行われるようになっています。 さて、中国から来た「茶=Cha」も西洋の「紅茶=Tea」も実はどちらも中国が発祥なんだそうです。 広東語系で「チャ=Cha」と呼ばれた茶葉は、主に海路で世界に広まり、 アラビアの「シャー=Shay」、トルコの「チャイ=Chay」ポルトガルや日本の「チャ=Cha」。 これに対し福建語系で「テ=Tai」と呼ばれた茶葉は、主に陸路経由で世界に広まり、 マレーシアの「テー=The」、ハンガリーの「テア=Tea」、スウェーデンの「テ=Te」、 英語の「ティー=Tea」となりました。 ------------------------------------------- 朝茶は七里帰っても飲め 朝に飲むお茶は災難よけなので、飲むのを忘れて旅に出たら、 たとえ七里の道を帰ってでも必ず飲むべきだという意味のことわざです。 仕事に出る前に必ずお茶を飲みますが、猫舌の私としては熱いのを入れられると、 フーフーしながら、時計を見ながら・・・ とてもティーブレイクとはいえません。 それでも、少し遅めの休日の朝には、ゆったりとミュージックブレイクの中で・・・ ------------------------------------------- 旧友との再会に、オープンテラスでカモミールティー、 しかし自分で書いたシナリオは、実現できません。
|