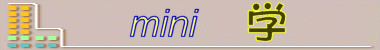 |
2008.5.31 |
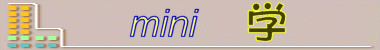 |
2008.5.31 |
日本で最初の時計が鐘を打った日が6月10日であることから、この日を時の記念日としています。 西暦671年、天智天皇が「漏刻(水時計)」を設置し、初めて人々に時刻を知らせたといわれています。 『日本書紀』によると4月25日ですが、新暦では6月10日にあたります。 江戸時代につくられた和時計は、日本独特の時計で、日の出から日の入り、日の入りから日の出の間をそれぞれ6等分した不定時法を前提として製作されています。 夏至の昼の長さは約15時間51分で、6等分した一時(いっとき)の長さは2時間38分。 夜の長さは8時間9分で一時の長さは1時間21分。 冬至の昼の一時は1時間49分で、夜の一時は2時間10分となります。 和時計が優れていた点は、時を刻む針の動きが変化し、昼の一時と夜の一時を区別していたことです。 明治維新を迎え、諸外国との交渉が盛んになるにつれ24時間の定時法が取り入れられ、日本独自に発達した和時計は姿を消していきました。 しかし、和時計で培われた技術は、日本の精密産業の発展に大きな貢献をもたらすことになりました。 少し話が飛びますが、私たちが日常生活を送っている場所は三次元の世界です。 一次元が線で、二次元は平面、そして三次元は立体的な空間、その三次元空間にもうひとつ「時間」の軸を加えると四次元空間になると考えられています。 一次元の世界では、線の上を往復することしかできません。 仮に、線の上に何かの物体を置かれたら、それをよけて通ることはできませんが、二次元の世界ならば平面ですから当然迂回します。 では、その邪魔な物体が限りなく横に長いものだとしたら、限りなく遠回りをしなくてはなりません。 立体的な空間を知らないために、物体を乗り越えることができないのです。 平面を紙のようなものだとして、その紙がゆがんで曲がったとしたら、その地点が二次元世界の地の果てということになります。 紙をさらに曲げて、反対側の一辺にくっつけたとします。 たとえばアリなど、三次元の生き物ならばその紙の上を伝って一周できますが、二次元の生物から見た場合、 「地の果てで消えた生き物が反対側から現れた」ことになります。 では四次元空間を想像してみます。 三次元に時間の軸を加えたのが四次元と考えられます、二次元の紙の平面を曲げたように、三次元の時間の軸を曲げるとどうなるでしょうか。 そうです、それがタイムトンネルなのです。 二次元の紙の端を反対側の一辺にくっつけたように、未来から過去へ、時空を自由に行き来できるのです。 筒井康隆の小説で「時をかける少女」という作品がありました。 20数年ほど前に大林宣彦監督、原田知世主演で映画化され、そのあとテレビドラマ化や最近ではアニメ映画としてリメイクされているようです。 ある日突然、時間を超える能力を持ってしまった少女の、不思議な経験と淡い恋心を描く作品で、キーワードはラベンダーでした。 この頃、ラベンダーの花は一般的でなかったというか、ただ私が知らなかっただけかもしれませんが、どんな香りなのかわかりませんでした。 友人から、「私の家のラベンダーです、」ということで、封書の中に押し花(半生状態?)で送られたのですが、 「香りがした?」と聞かれ、「・・・よくわからなかった、」 たぶんほのかな香りはしたと思うのですが、自分の想像では、甘い香り・・・と思っていたので、想像と現実にギャップがあり、ラベンダーの香りとして認識できなかったのかもしれません。 それからだいぶ時が経ちました。 今、我が家の庭のラベンダーは、ほんの少しうす紫色が見えてきました。
|