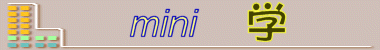 |
2007.9.1 |
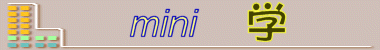 |
2007.9.1 |
地球上の生物のある種が絶滅すること自体は、それほど珍しいことではありません。 生命の歴史において無数に起きていることで、なかでも恐竜の絶滅は代表的なものです。 しかし人類の経済成長が地球上の生物に何らかの影響をもたらし、それによる種の絶滅が発生していることも事実だと言えます。 コウノトリが日本国内の自然界で巣立ちしたのは46年ぶりだったそうです。 自然界で43年ぶりに誕生した幼鳥が、人工巣塔から飛び立つ姿を何らかの形で見た人は多いと思います。 「兵庫県立コウノトリの郷」で、人里での野生に復帰させる事業として行なっているものです。 コウノトリを野生に復帰させるということは、コウノトリが住めるような自然環境を作ってやらなくてはなりません。 餌となるドジョウや蛙などが生息できる川や田んぼを、また巣を作るための高い木が茂る自然環境を作らなくてはなりません。 ドジョウや蛙が住める河川にするためには、川を単なる用水路にしない、農薬を使用しないなどの環境を整える必要があります。 人間が管理しやすいように、コンクリート等で護岸工事された用水や海岸線からは多くの生物が消えています。 人間が住みやすい環境にと考えたことが、もっと広い視点から見れば結果的には自分達の住む環境を破壊していることにもなります。 絶滅危惧種とは、急速な環境変化や乱獲などにより絶滅したり絶滅寸前に追いやられたりしている動植物のことですが、 その原因のほとんどは人間がかかわっています。 沖縄だけに住む固有種のヤンバルクイナも絶滅危惧種に指定されていますが、これは移入生物によるものです。 これには毒蛇のハブを退治するために人間が持ち込んだ、マングースが起因しています。 ハブ対マングースの戦いは、現地の観光としても使われているようですが、人間の興味本位の行為が動物たちにとっては生死を分けるものになります。 実はハブ退治を目的に離されたマングースですが、猛毒を持ったハブに向かうよりももっと簡単に獲られる相手を見つけました、それがヤンバルクイナです。 ヤンバルクイナは、マングースのような強力な肉食獣がいないのんびりとした環境で暮らしてきたため、突然現れた強敵に対してなすすべもなく激減してしまいました。 直接的な環境破壊だけでなく、外来生物の持込や移植などでも種の絶滅は引き起こされています。 日本の自然の中で生息していないはずのワニが下水道の中で見つかったり、噛みつきガメが周辺の川で発見されたり、これは人間の身勝手な行為以外の何物でもありません。 ワニが自然繁殖することはないと思いますが、外来のカメやピラニア、毒グモ、猛毒アリなどは心配です。 また、自然環境の話に戻りますが、 「ホタルを呼び戻そう」とか「ホタルの住める環境を・・・」などの運動が全国の各地で起こっているようです。 ホタルを保護するということは、コウノトリと同じように、住めるための環境を作らなくてはなりません。 ホタルが生息するためには、カワニナという貝がいる小川などが条件になります。 ホタルの幼虫は、カワニナを餌にするからで、そのカワニナは、泥の中の有機物や、石についた藻類、またドジョウやザリガニ、小魚の死肉を餌にしています。 「ホタルを保護しているのか、カワニナを保護しているのか分からなくなる」 という話が関係者の中にあるそうです。 もし、ホタルとカワニナがまったく関係なく、カワニナが絶滅の危機にあるということが分かったとき、果たしてカワニナを絶滅から救おうという運動が起こるでしょうか。 かわいいから、きれいだからということで保護することもまた、人間の身勝手なように思えます。 地球上の自然界では木々が倒れ、動物が死骸となりますが、やがてそれらは土に返ります。 でもただ自然に土になるわけではありません、それは微生物の働きによるものです。 微生物は地球上の生態系を形成する重要な役割を果たしてくれています。 あるデーターによると、地球上に生息する細菌の種は3万以上にのぼり、そのうち人間が発見して名前を付けているものは、その10%程度にすぎないそうです。 その中でも病原菌とされるのはまた一部で、地球上で人類とともに生きている細菌(微生物)の数はいかに多いかといえます。 天然痘が地球上で確認されたのは、10世紀以前だといわれていますが、1980年にWHOは根絶宣言を行い、つまり天然痘を人類が地球上から根絶したといえます。 しかし、ウイルスは現在ロシアとアメリカの研究所のガラス管の中で厳重に管理されています。 少し横道にずれたかもしれませんが、 もしハエやゴキブリが絶滅寸前になったら、人類はそれらを保護するでしょうか。 でもそんな世の中を考えてください、そんな環境の中で人間そのものが生きていけるのでしょうか、 人類が絶滅するとき、いったい誰が助けてくれるのでしょうか。
|
||||