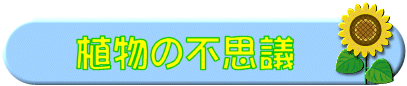 |
2004.4.24 |
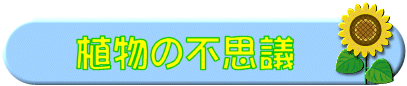 |
2004.4.24 |
 |
シロツメクサ (白詰草) またの名を クローバー まめ科 |
江戸時代に、「ギヤマン」や「びいどろ」と呼ばれたガラス工芸品がオランダから渡ってきました。 そのときに緩衝材として詰め込んだ枯れ草が、これであったことが名前の由来とされています。 シロツメクサの花は、小さな花が集まってひとつの花になっています、そして咲き終わった小さな花は下に垂れ下がります。 小さな花の寿命は短くても、これから咲くつぼみや、咲き終わってしまった花も集まっているから大きな花が咲き続けているように見えるのです。 これは、花を目立たせてミツバチを呼び寄せるためだと思われます。 またもうひとつの工夫は、この花の蜜は小さな花の奥のほうにあることです。 ミツバチがこの花の蜜を吸うとき、後ろ足で小さな花びらを押し広げて巧みに進入していきます。 力の弱い小さな蜂や、その他の虫たちはこのシロツメクサの花の前で門前払いに会うわけで、 シロツメクサは、こうして難関を潜り抜けて訪れるミツバチにおいしい蜜を与えるのです。 シロツメクサの蜜の入手方法を覚えたミツバチは、おいしい蜜を独占したようにシロツメクサの花ばかりを回ります。 これはシロツメクサにとっては大変都合のよいことで、シロツメクサ同士での花粉の受け渡しが容易になることです。 花と虫、また海中などの魚と他の生き物の中にも、こうしたパートナーが見かけられますが、不思議でもあり、またそれが自然なのかもしれません。
|